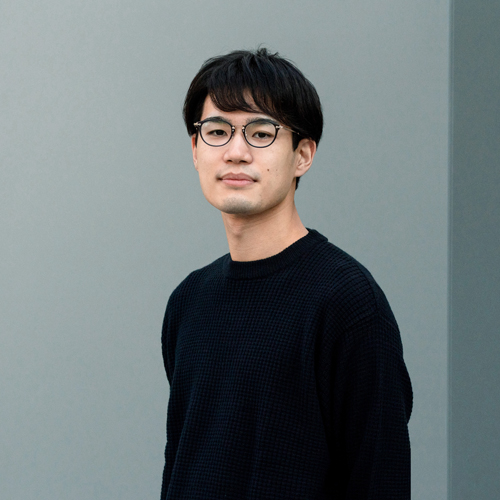IDEA
高齢者を「前向き」にさせるユニバーサルファッション
——株式会社ケアウィル 笈沼清紀インタビュー
Interviewee:Kiyonori Oinuma Interviewer&Introducer and Concluder:Yuko Shibata Main text writer:Hideto Mizutani

かつては閉鎖的なイメージのあった高齢者施設ですが、近年、積極的に施設を開放する傾向が強くなってきています。施設に備えつけられた地域交流室だけでなく、施設のイベントに地域住民を招待したり、多世代交流を促すまちづくりなど、様々なかたちで高齢者と地域住民の交流を促しています。そういった状況を受け、敷地内に地域住民が集まれるようなカフェや、玄関を通らずに外部から直接アクセスできる交流室など、施設の空間設計も変わりつつあります。
一方で、施設で過ごす高齢者の装いにはあまり進化が感じられません。1日のほとんどを室内で過ごす彼らの服装は、家着のような装いが主流です。体の制約や生活スタイルに適した服装でありながら、外部との交流に対して積極的に参加できるような服装とはどんなものなのでしょうか。
今回は、ハンディキャップを持つ方に対する衣料などの開発をされている、株式会社ケアウィルの笈沼清紀さんにお話を伺いました。大手企業の執行役員などの経歴を持つ笈沼さん。彼のマーケティング的視点と、当事者家族としての経験を融合させた取り組みは、当事者とその家族の思いを尊重するというプロセスの重要性に気づかせてくれました。

ケア衣料開発の原点となった当事者家族としての視点
——ケア衣料を作るに至った経緯を教えてください。
今は亡くなりましたが、私の父は、生前介護施設に入居していました。ただ、認知症の進行で夜中の徘徊が増えるなど施設に入居し続けることが難しくなり、亡くなる1年ほど前に精神科病棟に入院したんです。
入院してしばらくしたある時に病院の経営方針が変わり、ほぼ全員の患者さんが同じデザインの病院着をレンタルする仕組みになりました。その後、私と母で面会に行ったのですが、遠目では父と他の患者さんとの区別がつかなかったのです。そういった画一的な光景を目の当たりにしたのがきっかけですね。
父の介護度が進んでいくと、病院着が浴衣のような服からつなぎ服になっていきました。つなぎ服の首元は本人が服を脱げないようロックがかかっていたんです。それは、自分の排便を口にしたり、おむつを剥いでしまったりといった認知症に伴う問題行動を抑制するためでした。
——なるほど。病院や施設を見学することはよくありますが、つなぎ服の存在は初めて知りました。
面会で父がつなぎ服を着て現れたときは衝撃でした。そのときは要介護度5でしたから、本人の意思や感情の多くは表に出ていませんでした。でも、父がもし元気だったとして、この服を着せられたら何と言っただろうかと考えてしまいました。
また、つなぎ服を着せられている父の姿を見た瞬間に「もう病院から出てこれないのだ」と、私自身が自覚させられてしまいました。このまま家に戻ってくることもないだろうし、このまま病院で死を迎えていくのだろうと。服が私にそう思わせたのです。
僕ら家族からすれば”変わらない”父であるにもかかわらず、物理的に洋服は変わっていく。その変わってしまった服を通して、なぜ父の死を自覚させられるのかと、強い違和感を覚えました。

開発の中で得られた当事者の目線
——ケアウィルのプロダクトは、利用するシチュエーションが考え抜かれていると感じました。その中でも洗濯ネットバックは、利用者が自立して洗濯をこなすために作られていますね。
私たちが大事にしているのは、ケアウィルの「ウィル」の部分、病気や障がいのある方の「意思」を尊重することです。先ほどのつなぎ服は、介護をする人にとっての効率性やリスク管理といった都合を優先した結果生まれたものだと感じました。
ケアウィルでは、心身がどんな状態にあったとしても、当事者本人には意思があると考えています。だから、本人の意思を中心に、自律的に生活ができるように支援する製品を作っています。
たとえば、洗濯ネットバッグも、動作に伴う痛みやストレスから、こまめに洗濯をすることを諦めてしまった人たちが、このバッグを使うことで、再び洗濯ができるようになって欲しいという思いから作られました。洗濯という作業を通じて、日々の生活に前向きな思いを取り戻せると良いなと。本人の意思を尊重し、気持ちが前向きになるお手伝いをしたい。それが、ケアウィルがものづくりで一貫して大切にしていることです。

洗濯ネットバッグ
——アームスリングケープも同様に利用者本人の意思を尊重されていると思います。特に、肩を痛めている方の利用を想定していると思いますが、実際はどのような方が利用されているのでしょうか。
実際使われている方の半分ほどは60歳を超えています。症状で言えば、脳血管障害による弛緩性麻痺を持つ方が7割を占めていて、その他は高齢者にも多い腱板断裂・損傷、重度の五十肩などの肩の整形疾患です。

腕を通してから首を通すという、特殊な着方をするアームスプリングケープ
着用方法はこちらから!!➡️➡️➡️👭👬株式会社ケアウィルHP👭👬
服作りをする過程で、当事者の多くが好きな服を着ることを諦めている場面が多いと感じました。当事者のお話を聞いていると、色違いの同じ服を着ていらっしゃることがよくあります。それくらい、既製服の中から着やすい服を探すのがすごく難しいんですね。
でもそれは、病気や障がいになる前からではありません。いくつかの過程を経て「諦め」に至っている。最初からおしゃれを諦めていたわけではなく、最初は、かつて自分が好きなお洋服を買っていた店を訪れています。でも自分が着れる服が見つけられず、途方に暮れる。その連続の中で「自分が着たい服をもう着れないのだ」と諦めてしまう。そして、介護用品のパジャマや、ケアマネージャーが教えてくれた服を着るようになる。
おしゃれをしたいというご本人の意思は必ずあります。意思はあるけれども選択肢がない。まさか着れるなんて思っていないから諦めてしまうんです。私たちはものづくりによって、当事者の皆さんが諦めていたことができるようになり、少しでも日々を前向きに過ごせるように応援をしたいのです。

試作品A:首を通した後に腕を通すという着方で、腕にハンディキャップを持つ当事者には着づらい初期の試作品。

試作品B:服の内部で様々な寸法調整ができるように多機能にした結果、ファスナーなどが増えて重くなり、着用の負担が大きかった試作品。

試作品C:ポンチョ型に移行した試作品。デザイン性は増したものの、ファスナーがあることで、腕にハンディキャップのある当事者だけでは着にくい。

試作品D:腕を通してから首を通すという着方に辿り着いた現行品に近い試作品。普段着の上から羽織るようなポンチョ型の商品が完成した。
支援者と当事者の視点のギャップ
——以前、川崎市と車椅子用のレインウェアを開発されていましたね。どのようなプロセスで製品開発を行ったのでしょうか。
ご縁があって川崎市の複合福祉施設「ふくふく」に勤めるリハビリ専門職の方から、「レインウェア」の特注品の製作依頼をいただいたのがはじまりでした。
利用者さんが普段使われているバイクメーカーのレインウェアを拝見したところ、ぼろぼろになっていたんです。「このレインウェアをどうにかしてほしい。自分で簡単に着脱ができて、友人とカフェに行くときに畳んで傍らにおいても可愛いウェアが欲しい。」というのが利用者さんからのご要望でした。お話を伺いながら、レインウェアには市場性があるかもしれないとも感じました。
今までも車椅子の方向けのレインウェアは存在しましたが、繭のように全身を覆う形のものでした。利用者本人にそれを着たことがあるか聞いたところ、着たことはあるものの介助者がいて初めて着ることができるものなので、着なくなっていったと言うんです。
——世の中には、介助しやすいという視点のプロダクトしかなかったということですね。
そうなんです。レインウェアの開発過程はとても面白くて、膝のカーブは車椅子にぴったりの方が良いんじゃないかとか、利用者さんは足がほとんど動きませんから雨の日はブーツを履いた時にブーツをしっかり覆ったほうが良いんじゃないかとか、色々な意見が当事者、担当の理学療法士、作業療法士から出ました。
でも大事なのは、先ほども言ったように当事者中心であるかどうかです。利用者さんに改めて聞いたところ、足なんて多少濡れても良いから、長くてまとわりつくのは着たくないと。また、友達とカフェに行ったときに、簡単に脱げてどこかに置けるサイズを求めていたんです。

画像左:制作風景 画像右:試着して外出テスト
介助されるご家族は靴が濡れないことをご希望とのことでしたが、利用者さんは違った。理学療法士からはプロとして車輪に干渉しないように調整用のベルトが必要だという意見が出ましたが、そうするとデザインは複雑化するし価格も高くなってしまう。本人と支援する側では、生活におけるリスクの考え方が違うと気づかされました。
すべてを満たそうとしても、良いものづくりはできない。私は、最終的には当事者が求めることを最優先することにしています。時として、デザインを捨てることも大事だと思っています。
ケアのプロを巻き込んだチーム編成
——現在の開発チーム編成を拝見すると、理学療法士や作業療法士の方が広報やマーケティング部門を担当されているのがとても印象的でした。開発チームの編成で意識されている点を教えてください。
実は、今の社内チームを作る前に、一度大きな失敗を経験しました。マーケティングやクリエイティブのプロを入れてプロダクトを開発したのですが、世の中に全く伝わらなかったんです。愕然としました。
なぜうまくいかなかったのか?失敗した理由を突き詰めていくと、結局プロダクトの「表現」を外注してしまったことにありました。関わってくれたプロの方々は皆さん素晴らしかったけれど、ご自身が病気や障がいのある当事者やそのご家族ではない。僕は父の看護、介護を長らくしてきたから良し悪しを言うことはできても、その表現の多くを任せてしまった。だから表現に生々しさがない。
そこで、その後は医療介護の専門職、もしくはご自身が介護をされている方に入ってもらうようにしました。さらに、プロダクトを世に出す前の段階から、作業療法士や理学療法士といったリハビリを支援する医療専門職の方に公開するというコミュニケーションに変えたんです。発売前のサンプルが完全にできあがってない段階で現場の方に送り、感想を聞きました。
そうすると発売した途端、作業療法士の方たちがSNSで拡散してくれたんです。こんな使い方があるよ!と、SNSを通して私たちが想像していない使い方も教えてくれました。

——情報が拡散している段階で様々な使い方が見つかるんですね。現在は外注せずに自走可能なチームを作っているのでしょうか。
現在は、当事者の方やご家族の方向けの表現を内製化しています。プロダクトの紹介資料も私が作っています。内製化すると見た目のクオリティは落ちるかもしれませんが、当事者には誠実に、正確に伝わる。私たちが内製したほうがリアルだし、そこにはストーリーがあります。SNSではデジタルな手法や表現が進んでいますが、私たちのプロダクトでは逆にリアルな表現の方が皆さんに共感してもらえる気がします。
当事者だけでなく、家族を意識したものづくりを
——最後になりますが、今後の目標と展望を教えてください。
戦後日本では核家族化が進展してきました。私は42歳ですが、その変化の中で生きてきました。今後も核家族が家族の形の主流であり続けるのでしょうか。私は、大都市に移り住んで進学・就職する生き方ではなく、親子の物理的な距離がより近い生き方が、これからは主流になってくるのではと考えています。
そして、金融のデジタル化を背景に、金銭的にも親子は緊密になっていくでしょう。私たちの祖父母の世代では、亡くなった後に資産の在り処が分からないということが良くありました。でも、デジタル化が進んだ今は、子どもがスマホなどを使って親の資産を管理することもできます。
そういった状況の中で、当事者だけでなくその家族の「意思」も尊重したものづくりをしていきたいです。財布が同じということは、子どもが高齢の親の支払いもすることになるのですから。
初めてケアウィルの商品を目にした際、その印象は「デザイン性が高く、従来の高齢者向け商品とは一線を画している」というものでした。そのため、実際に高齢者に受け入れられるのかという疑念を抱きながら、今回のインタビューに臨みました。しかし、インタビューによって、このデザインが信頼性のある根拠に基づいていることを知り、ケアウィルの商品に対する認識が完全に変わりました。
「デザイン性の高いケア衣料」という形で具現化された、笈沼さんが思い描く家族に対するビジョンは、家族という概念を新たな視点から見つめ直す必要があることを、私たちに示唆しています。さらに、将来的にこの視点は、魅力的な高齢者施設の設計においても重要な意味を持つことになるでしょう。